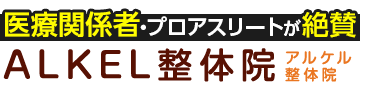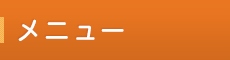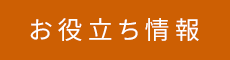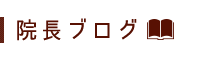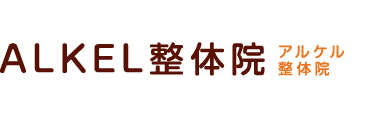脊柱管狭窄症の原因とタイプ別の症状、適切な治療法の選び方
脊柱管狭窄症の原因でお悩みですか?この記事では、脊柱管狭窄症の主な原因を、加齢、遺伝、生活習慣といった観点から分かりやすく解説します。さらに、腰部と頸部のタイプ別の症状や、それぞれの症状に適した治療法の選び方、そして、脊柱管狭窄症を悪化させないための予防法まで網羅的にご紹介します。この記事を読めば、脊柱管狭窄症の全体像を理解し、ご自身に合った対策を立てることができます。原因不明の腰痛や足のしびれ、手足の違和感にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 脊柱管狭窄症とは何か
脊柱管狭窄症とは、背骨の中を通る脊髄神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、神経が圧迫され、様々な症状を引き起こす病気です。脊柱管は、背骨を構成する椎骨が積み重なってできたトンネルのような構造で、その中を脳から続く脊髄神経が通っています。この脊柱管が、加齢や生活習慣、遺伝などの要因によって狭窄することで、神経が圧迫され、痛みやしびれなどの症状が現れます。
脊柱管狭窄症は、主に腰部と頸部に発生し、それぞれ腰部脊柱管狭窄症、頸部脊柱管狭窄症と呼ばれます。腰部に発生する方が多く、中高年以降に発症しやすいのが特徴です。また、脊柱管が狭くなる場所や程度、神経の圧迫のされ方によって症状は様々です。そのため、早期に適切な診断と治療を受けることが重要です。
1.1 脊柱管狭窄症の分類
脊柱管狭窄症は、狭窄が起こる部位によって大きく2つに分類されます。
|
分類 |
説明 |
主な症状 |
|
腰部脊柱管狭窄症 |
腰部の脊柱管が狭窄する |
腰痛、下肢のしびれや痛み、間欠性跛行 |
|
頸部脊柱管狭窄症 |
頸部の脊柱管が狭窄する |
首や肩の痛み、腕や手のしびれや痛み、歩行障害 |
1.2 脊柱管狭窄症とよく似た病気
脊柱管狭窄症は、症状が他の病気と似ている場合があり、鑑別診断が重要です。例えば、腰部脊柱管狭窄症の場合、腰椎椎間板ヘルニア、変形性腰椎症、坐骨神経痛などと症状が類似していることがあります。これらの病気は、それぞれ原因や治療法が異なるため、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。正確な診断を受けることで、適切な治療を受けることができます。
特に、腰椎椎間板ヘルニアは、椎間板の一部が飛び出して神経を圧迫する病気で、腰痛や下肢のしびれなどの症状が現れます。変形性腰椎症は、加齢などによって腰椎が変形し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫されることで、臀部や太もも、ふくらはぎなどに痛みやしびれが生じる病気です。これらの病気と脊柱管狭窄症は、症状が似ている場合があるため、注意が必要です。
2. 脊柱管狭窄症の主な原因
脊柱管狭窄症は、様々な要因が複雑に絡み合って発症するといわれています。主な原因として、加齢による変化、遺伝的要因、生活習慣などが挙げられます。その他にも、過去の怪我や病気なども影響することがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
2.1 加齢による変化
脊柱管狭窄症の最も大きな原因は、加齢に伴う脊柱の変形です。年齢を重ねると、椎間板の弾力性が失われ、薄くなったり、変形したりします。椎間板が薄くなることで、椎骨同士の間隔が狭まり、脊柱管が圧迫されるのです。また、椎間板の変形も脊柱管を狭くする一因となります。さらに、加齢とともに靭帯が肥厚したり、骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨の突起が形成されることもあり、これらも脊柱管を狭窄させる原因となります。
|
組織 |
加齢変化 |
脊柱管への影響 |
|
椎間板 |
弾力性の低下、変形、突出 |
脊柱管の圧迫 |
|
靭帯 |
肥厚、硬化 |
脊柱管の圧迫 |
|
椎骨 |
骨棘形成、変形 |
脊柱管の圧迫 |
2.2 遺伝的要因
脊柱管狭窄症は、遺伝的な要因も関係していると考えられています。生まれつき脊柱管が狭い体質の人や、特定の遺伝子を持つ人は、脊柱管狭窄症を発症するリスクが高いといわれています。家族に脊柱管狭窄症の患者がいる場合は、自身も発症する可能性があることを認識しておく必要があります。ただし、遺伝的要因だけで発症するわけではなく、後天的な要因が重なることで発症に至ると考えられています。
2.3 生活習慣
長時間のデスクワークや、重いものを持ち上げるなど、脊柱に負担がかかる生活習慣は、脊柱管狭窄症のリスクを高める可能性があります。また、運動不足や肥満も、脊柱への負担を増大させる要因となります。逆に、適度な運動は、脊柱周囲の筋肉を強化し、脊柱の安定性を高めるため、脊柱管狭窄症の予防に繋がります。
2.3.1 姿勢
猫背などの悪い姿勢は、脊柱に負担をかけ、脊柱管狭窄症を悪化させる可能性があります。正しい姿勢を意識することで、脊柱への負担を軽減し、症状の進行を抑制することができます。
2.3.2 運動
適度な運動は、脊柱周囲の筋肉を強化し、脊柱の安定性を高めるため、脊柱管狭窄症の予防に効果的です。ウォーキングや水泳など、脊柱に負担をかけにくい運動がおすすめです。しかし、激しい運動や無理な姿勢は、逆に症状を悪化させる可能性があるので注意が必要です。
2.3.3 体重管理
過剰な体重は、脊柱への負担を増大させるため、脊柱管狭窄症のリスクを高めます。適正な体重を維持することで、脊柱への負担を軽減し、症状の予防・改善に繋がります。
2.4 その他の原因
加齢、遺伝、生活習慣以外にも、脊柱管狭窄症を引き起こす原因はいくつかあります。過去に脊柱を骨折したり、椎間板ヘルニアなどを患った経験がある場合、脊柱が変形し、脊柱管が狭窄することがあります。また、関節リウマチや強直性脊椎炎などの炎症性疾患も、脊柱管狭窄症の原因となることがあります。さらに、まれに、脊柱腫瘍が脊柱管を圧迫し、狭窄症を引き起こすこともあります。
3. 脊柱管狭窄症のタイプ別の症状
脊柱管狭窄症は、発生する部位によって症状が異なります。大きく分けて、腰部に起こる腰部脊柱管狭窄症と、首に起こる頸部脊柱管狭窄症の2つのタイプがあります。それぞれの症状について詳しく見ていきましょう。
3.1 腰部脊柱管狭窄症
腰部脊柱管狭窄症では、神経が圧迫されることで、下半身に様々な症状が現れます。代表的な症状には、間欠性跛行と安静時の痛みやしびれがあります。
3.1.1 間欠性跛行
間欠性跛行は、歩行時に足やお尻にしびれや痛み、だるさを感じ、しばらく休むとまた歩けるようになるという症状です。しばらく歩くと再び症状が現れ、また休むことを繰り返します。進行すると、少し歩いただけでも症状が現れるようになります。自転車に乗っているときは症状が出ないことが多いのも特徴です。
3.1.2 安静時の痛みやしびれ
安静時にも、腰や足に痛みやしびれ、冷感、灼熱感などが現れることがあります。夜間や朝方に症状が強くなる場合もあります。また、前かがみになると症状が軽減し、仰向けで寝ると症状が悪化することがあります。これは、前かがみになると脊柱管が広がり、神経への圧迫が軽減されるためです。
3.2 頸部脊柱管狭窄症
頸部脊柱管狭窄症は、首の脊柱管が狭窄することで、主に上肢に症状が現れます。代表的な症状には、手のしびれや痛み、歩行障害などがあります。
3.2.1 手のしびれや痛み
頸部脊柱管狭窄症の初期症状として、片方または両方の手にしびれや痛み、感覚の鈍化などが現れることがあります。症状は、指先から腕全体に及ぶ場合もあり、細かい作業がしにくくなることもあります。また、首を後ろに反らすと症状が悪化することがあります。
3.2.2 歩行障害
頸部脊柱管狭窄症が進行すると、足元がおぼつかなくなったり、歩行が困難になることがあります。これは、脊髄が圧迫されることで、足への神経伝達がうまくいかなくなることが原因です。また、排尿障害や排便障害が現れる場合もあります。
|
症状 |
腰部脊柱管狭窄症 |
頸部脊柱管狭窄症 |
|
痛みやしびれの部位 |
腰、臀部、太もも、ふくらはぎ、足先など下半身 |
首、肩、腕、手、指先など上半身 |
|
特徴的な症状 |
間欠性跛行、前かがみで楽になる |
手の細かい動作が困難、首を反らすと悪化 |
|
その他 |
排尿・排便障害(まれ) |
歩行障害、排尿・排便障害(進行した場合) |
これらの症状は、他の病気でも現れることがあるため、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。早期発見、早期治療によって、症状の進行を抑制し、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
4. 脊柱管狭窄症の診断方法
脊柱管狭窄症の診断は、患者さんの症状や病歴、そして様々な検査結果を総合的に判断して行います。問診では、いつから症状が現れたのか、どのような時に症状が悪化するのか、日常生活にどのような支障が出ているのかなどを詳しく伺います。また、過去の病歴や現在の健康状態についても確認します。
次に、身体診察を行います。姿勢や歩行の様子を観察し、脊椎の動きや神経の状態をチェックします。触診では、脊椎の圧痛や筋肉の緊張などを確認します。さらに、神経学的検査を行い、感覚や反射、筋力などを評価することで、神経の圧迫の程度を判断します。
4.1 画像検査
画像検査は、脊柱管狭窄症の診断に不可欠です。主に以下の検査が行われます。
4.1.1 X線検査
X線検査では、脊椎の形状や骨の状態、椎間板の狭小化などを確認できます。脊柱管狭窄症の疑いがある場合、まず初めにX線検査が行われます。X線検査は、脊椎の全体像を把握するために有用です。
4.1.2 MRI検査
MRI検査では、脊髄や神経根、椎間板、靭帯などの状態を詳細に確認できます。脊柱管の狭窄の程度や、神経が圧迫されている様子を鮮明に映し出すことができるため、脊柱管狭窄症の診断に最も重要な検査です。
4.1.3 CT検査
CT検査は、骨の状態をより詳細に評価するために用いられます。特に、骨棘の形成や椎間関節の肥厚など、骨性の変化を詳しく確認したい場合に有効です。
4.1.4 脊髄造影検査
脊髄造影検査は、造影剤を用いて脊髄や神経根の状態を詳しく調べる検査です。MRI検査で診断が難しい場合や、手術を検討する場合に行われることがあります。脊髄造影検査は、神経の圧迫部位や程度を正確に把握するのに役立ちます。
|
検査方法 |
目的 |
特徴 |
|
X線検査 |
脊椎の形状、骨の状態、椎間板の狭小化を確認 |
簡便で広く行われている検査 |
|
MRI検査 |
脊髄、神経根、椎間板、靭帯の状態を確認 |
脊柱管狭窄症の診断に最も重要な検査 |
|
CT検査 |
骨の状態を詳細に評価 |
骨棘の形成や椎間関節の肥厚の確認に有効 |
|
脊髄造影検査 |
脊髄や神経根の状態を詳細に調べる |
手術を検討する場合などに行われる |
これらの検査結果を総合的に判断し、脊柱管狭窄症の確定診断を行います。また、他の疾患との鑑別も重要です。坐骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニアなど、似たような症状を引き起こす疾患もあるため、これらの疾患との鑑別診断が必要となる場合もあります。 診断結果に基づいて、適切な治療方針が決定されます。
5. 脊柱管狭窄症の治療法
脊柱管狭窄症の治療は、症状の程度やタイプ、患者さんの状態に合わせて、保存療法と手術療法を使い分けていきます。基本的には、まず保存療法を行い、効果が不十分な場合や症状が進行している場合に手術療法を検討します。
5.1 保存療法
保存療法は、手術を行わずに症状の緩和を目指す治療法です。痛みやしびれを軽減し、日常生活の質を向上させることを目的としています。
5.1.1 薬物療法
痛みやしびれを軽減するために、様々な薬物が使用されます。
|
薬の種類 |
作用 |
|
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) |
炎症を抑え、痛みを軽減します。ロキソニン、ボルタレンなどが代表的です。 |
|
神経障害性疼痛治療薬 |
神経の痛みを抑えます。リリカ、サインバルタなどが用いられます。 |
|
筋弛緩薬 |
筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。ミオナールなどが使用されます。 |
5.1.2 理学療法
ストレッチや筋力トレーニングなどの運動療法を通して、脊柱周辺の筋肉を強化し、柔軟性を高めることで、症状の改善を目指します。姿勢の改善指導なども行われます。
5.1.3 装具療法
コルセットなどの装具を装着することで、腰椎を安定させ、痛みを軽減します。症状が強い時期や、長時間の立ち仕事や歩行が必要な場合に有効です。
5.2 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、神経症状が進行している場合、手術療法が検討されます。手術には様々な方法がありますが、いずれも脊柱管を狭窄している部分を広げ、神経への圧迫を取り除くことを目的としています。
5.2.1 除圧術
脊柱管を狭窄させている骨や靭帯の一部を除去し、神経への圧迫を取り除く手術です。脊柱管狭窄症の手術で最も一般的な方法です。
|
手術の種類 |
特徴 |
|
椎弓切除術 |
椎弓と呼ばれる骨の一部を除去する手術です。 |
|
椎間板ヘルニア摘出術 |
飛び出した椎間板の一部を除去し、神経への圧迫を取り除く手術です。脊柱管狭窄症に伴って椎間板ヘルニアが生じている場合に行われます。 |
|
脊柱固定術 |
不安定な脊椎を固定する手術です。脊椎すべり症などを合併している場合に行われます。 |
手術療法は神経への圧迫を直接的に取り除くことができるため、症状の改善が期待できます。しかし、手術にはリスクも伴いますので、医師とよく相談し、手術の必要性やリスクについて十分に理解した上で判断することが重要です。
6. 脊柱管狭窄症の予防法
脊柱管狭窄症は、完全に予防できる病気ではありませんが、進行を遅らせたり、症状の悪化を防いだりするための対策はあります。日頃から意識して生活習慣を改善することで、将来の脊柱管狭窄症リスクを低減できる可能性があります。
6.1 姿勢の改善
正しい姿勢を維持することは、脊柱への負担を軽減し、脊柱管狭窄症の予防に繋がります。猫背や反り腰は、脊柱に過剰な負担をかけるため、意識的に背筋を伸ばし、良い姿勢を保つようにしましょう。
具体的には、以下の点に注意してください。
- 立っている時は、お腹に軽く力を入れて、背筋を伸ばす。
- 座っている時は、深く腰掛け、背もたれを利用する。足を組むのは避けましょう。
- デスクワークをする際は、モニターの位置を目の高さに合わせ、キーボードとマウスは体に近い位置に置く。
6.2 適度な運動
適度な運動は、背骨周りの筋肉を強化し、脊柱を支える力を高めます。ウォーキング、水泳、ヨガなどは、脊柱への負担が少なく、効果的な運動です。ただし、激しい運動や無理な姿勢は逆効果となる場合があるので、自分の体力に合った運動を選び、痛みを感じたらすぐに中止しましょう。
|
運動の種類 |
効果 |
注意点 |
|
ウォーキング |
全身の血行促進、筋力強化 |
正しい姿勢で歩く |
|
水泳 |
浮力による関節への負担軽減、全身運動 |
水温に注意 |
|
ヨガ |
柔軟性向上、体幹強化 |
無理な姿勢は避ける |
6.3 体重管理
過剰な体重は、脊柱への負担を増大させ、脊柱管狭窄症のリスクを高めます。適正体重を維持するために、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。特に、内臓脂肪の蓄積は腰への負担を増大させるため、腹囲の管理も重要です。
6.4 禁煙
喫煙は、血管を収縮させ、血行不良を引き起こします。血行不良は、脊柱への栄養供給を阻害し、脊柱管狭窄症の進行を早める可能性があります。禁煙することで、血行が改善され、脊柱の健康維持に繋がります。
6.5 適切な睡眠
睡眠不足は、体の回復を妨げ、痛みを増強させる可能性があります。質の良い睡眠を十分に取ることで、体の疲労を回復し、脊柱への負担を軽減できます。寝具にも気を配り、体に合ったマットレスや枕を選びましょう。
6.6 定期的な検診
早期発見、早期治療は、脊柱管狭窄症の進行を抑制するために重要です。特に、加齢とともにリスクが高まるため、少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診し、適切な検査を受けるようにしましょう。
7. 脊柱管狭窄症が悪化するとどうなるか
脊柱管狭窄症を放置したり、適切な治療を受けなかったりすると、症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。初期段階では軽い痛みやしびれでも、進行すると歩行困難になったり、排尿・排便障害が出現したりするなど、深刻な事態になりかねません。だからこそ、早期発見・早期治療が重要なのです。
7.1 神経症状の悪化
脊柱管狭窄症の悪化に伴い、神経への圧迫が強くなります。その結果、下肢の痛みやしびれ、感覚障害、筋力低下などが進行し、日常生活に大きな影響を及ぼします。
7.1.1 間欠性跛行の悪化
初期段階では、しばらく歩くと痛みやしびれで歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになる「間欠性跛行」が現れます。悪化すると、この歩ける距離がどんどん短くなり、最終的には少し歩いただけでも痛みやしびれが生じるようになります。
7.1.2 安静時痛の出現
初期は安静にしていると症状が軽減されることが多いですが、悪化すると安静時にも痛みやしびれが続くようになります。夜間痛で睡眠不足に陥ることもあり、生活の質が著しく低下します。
7.1.3 膀胱直腸障害
重症化すると、膀胱や直腸を支配する神経も圧迫され、尿失禁や便失禁、残尿感、排便困難などの膀胱直腸障害が現れることがあります。これは非常に深刻な症状であり、日常生活に大きな支障をきたします。緊急性を要する場合もあるので、すぐに専門医に相談する必要があります。
7.2 脊髄の圧迫による症状
脊柱管狭窄症が進行すると、脊髄が圧迫され、様々な神経症状が現れます。頸部脊柱管狭窄症の場合、手のしびれや痛み、巧緻性の低下(細かい動作が難しくなる)などが起こります。また、下肢の痙縮(筋肉が硬直し、突っ張った状態になる)、歩行障害なども見られることがあります。
7.3 日常生活への影響
|
症状 |
日常生活への影響 |
|
痛みやしびれ |
長時間の歩行や立ち仕事が困難になる。趣味やスポーツを楽しめなくなる。 |
|
歩行障害 |
外出が困難になる。買い物や通院に支障が出る。転倒のリスクが高まる。 |
|
膀胱直腸障害 |
尿失禁や便失禁により、精神的な負担が増大する。外出を控えがちになる。 |
|
手のしびれや痛み |
着替えや食事、字を書くなどの日常動作が困難になる。仕事や家事に支障が出る。 |
脊柱管狭窄症が悪化すると、上記のように日常生活の様々な場面で支障をきたし、生活の質が低下します。症状の進行を食い止め、快適な生活を送るためには、早期に適切な治療を受けることが重要です。少しでも気になる症状があれば、早めに専門医に相談しましょう。
8. 脊柱管狭窄症の専門医の選び方
脊柱管狭窄症の適切な診断と治療を受けるためには、専門医を選ぶことが重要です。どの医師に相談すれば良いのか迷う方もいらっしゃるかと思いますので、専門医選びのポイントをいくつかご紹介します。
8.1 専門領域を確認する
脊柱管狭窄症の治療は、整形外科が専門領域です。整形外科の中でも、脊椎外科を専門とする医師を選ぶと、より専門性の高い診療を受けることができます。
8.2 実績と経験を調べる
脊柱管狭窄症の治療には、豊富な経験と実績が重要です。医師の経歴や所属学会、専門とする治療法などを確認することで、医師の専門性や経験をある程度判断することができます。ホームページなどで医師の紹介がされている場合もありますので、参考にしてみてください。
8.3 セカンドオピニオンも検討する
診断や治療方針に迷う場合は、セカンドオピニオンを受けることも有効です。他の医師の意見を聞くことで、より納得のいく治療法を選択することができます。セカンドオピニオンは、患者さんの権利として認められています。
8.4 コミュニケーションを重視する
医師との良好なコミュニケーションは、治療の成功に不可欠です。自分の症状や不安をしっかりと伝えられる医師を選び、疑問点があれば積極的に質問するようにしましょう。また、医師の説明を理解しやすいと感じることも大切です。
8.5 医療機関の設備を確認する
脊柱管狭窄症の診断には、MRIやCTなどの画像検査が重要です。高度な医療機器を備えた医療機関を選ぶことで、より正確な診断を受けることができます。また、リハビリテーション設備が充実している医療機関であれば、術後のリハビリテーションもスムーズに行うことができます。
8.6 通院の利便性を考慮する
脊柱管狭窄症の治療は、長期にわたる場合もあります。そのため、自宅や職場から通いやすい医療機関を選ぶことも重要です。通院の負担が少なく、継続的に治療を受けることができます。
8.7 情報収集の方法
|
方法 |
メリット |
デメリット |
|
インターネット検索 |
手軽に情報収集できる |
情報の信憑性を見極める必要がある |
|
医療機関のホームページ |
医師の経歴や専門分野、医療機関の設備などが確認できる |
情報が偏っている可能性がある |
|
かかりつけ医からの紹介 |
信頼できる情報を得られる |
紹介状が必要な場合がある |
|
家族や友人からの口コミ |
生の声を聞ける |
主観的な意見である場合が多い |
これらのポイントを参考に、自分に合った専門医を見つけて、適切な治療を受けてください。
9. まとめ
脊柱管狭窄症は、主に加齢による変化や遺伝的要因、生活習慣などが原因で脊柱管が狭くなり、神経を圧迫することで様々な症状を引き起こす病気です。腰部脊柱管狭窄症では、間欠性跛行や安静時の痛みやしびれが現れ、頸部脊柱管狭窄症では、手のしびれや痛み、歩行障害などがみられます。症状や進行度に応じて、薬物療法、理学療法、装具療法などの保存療法や、手術療法が選択されます。早期発見・早期治療が重要となるため、少しでも気になる症状があれば、整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。日頃から正しい姿勢を保つ、適度な運動をする、バランスの良い食事を摂るなど、生活習慣にも気を配り、脊柱管狭窄症の予防に努めることも大切です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。